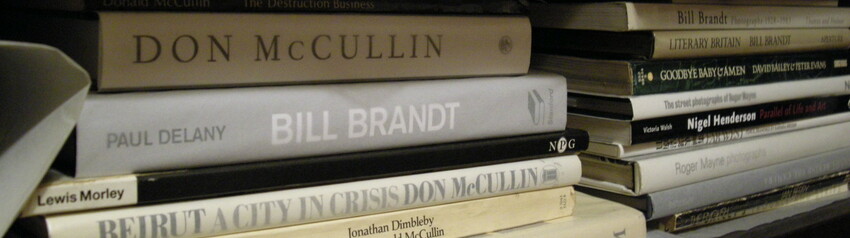映画の紹介と批評

●ケネス・ロナーガン監督『マンチェスター・バイ・ザ・シー』(アメリカ合衆国、2016年)。
「ハリウッド映画」や「アメリカ映画」のステレオタイプを見事に裏切る映画で、ハッピーエンドもエンターテイメントも、スペクタクルもフィール・グッドの要素も、微塵も感じられない。打ち勝つことのできない残酷な経験というものが人生にはあるということを、まずはまっすぐ淡々と示すことに成功した緻密なリアリズム映画である。比較をするつもりはないが、イギリスの映画監督マイク・リーを思い起こさせる作風だ。
にもかかわらず、2017年度アカデミー賞の主演男優賞と脚本賞、英国アカデミー賞の主演男優賞とオリジナル脚本賞、全米映画批評家協会賞の主演男優賞、助演女優賞、脚本賞など200を超える映画賞を受賞している。俳優のマット・デイモンがプロデューサー。
主人公のリー・チャンドラーは、その経験から逃げて別の人生を探すことができない不器用な、実直な、めんどうくさい労働者階級の男である。小さな町で、バーで酔って些細なことをきっかけに居合わせた男客を殴り殴り返されることで、かろうじて鬱屈する精神の均衡を維持しているような男である。噂はすぐに広まり、見つけたくても仕事先なども見つかりようがない。
しかし、打ち負かすことのできない経験から逃れられないダメ男の苦悩を描いただけの哀しい映画ではない。もう一人の主人公である高校生の甥パトリックの後見人としてリーが果たす役割をみれば、この映画が過去の人生の失敗や人間の暗部を主題にした映画ではなく、友情と連帯、保護と成長、(男同士の絆を基盤にした)新しい家族形成の成功を標した希望の映画なのである。
マンチェスター・バイ・ザ・シーは、アメリカ合衆国のボストン郊外の人口5千人ほどの小さな港町の名前である。その町の名前をそのままタイトルに使っているあたりにも監督の意思表示を感じるが。労働者階級固有の自律的な生活文化とそのサヴァイヴァル戦略の存在も、巧みに表現されている。甥のパトリックが、原理主義的なキリスト教徒と再婚した実母を訪ねる短いエピソードには、中流階級の排他的文化価値観への抵抗が鮮烈に描かれている。
本作は2016年1月にサンダンス映画祭で初上映され、通販最大手の参加のアマゾン・スタジオが、米国内での配給権を1,000万ドル(10億円)で買い取ったという。ソニー・ピクチャーズやユニヴァーサル・スタジオを上回る値だったらしい。日本でもアマゾンが、プライム・ビデオのサービスでオンライン鑑賞を提供している。筆者も(不本意だが)このサービスを利用して鑑賞した。
(2018年2月10日、オンラインにて鑑賞)

●サミュエル・マオズ監督『運命は踊る』(イスラエル・ドイツ・フランス・スイス、2017年)。
マオズ監督はイスラエルの作家であり、彼の作品を観たのはこれが初めてである。20・21世紀現代世界の重要問題を、ギリシャの古典悲劇のような普遍的な不条理の形式におさめつつ、その不条理を解決しようとしないイスラエルを鋭く撃った高硬度の作品。
ここでいう「不条理」とは、パレスチナ‐イスラエル戦争のことである。戦争の虚しさ、耐え難い退屈、無意味さ、言い知れぬ恐怖――それらは戦場だけではなく、日常生活の細部のひだまで浸透し、イスラエル社会とそこで暮らす人びとの極めて私的な親密圏に巣くい、人びとをゆっくりとむしばんでいる。
しかし、世界各地の戦場から遠く離れているかにみえる日本社会も、そこで生きる私たちも、この不条理感に冒され、慣れ親しんでいるのではないか。横柄で鈍感、攻撃的で不寛容、説明なしに既成事実を積み上げる、都合の悪いことはなかったことにする政治文化の汚染の中で、自分たちが狂っていくことにも無自覚になりつつある悪夢を観ているかのようにこの映画を観た。長くつきまとう佳作である。
インタビューで、ヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞した前作『レバノン』から8年も間が空いたことを問われたマオズ監督が次のように(当然にも苛立って)答えているのもいい。「かかったのは3年です。というのも他のこともしていますから。私は本を書き、絵を描き、子育てと、常にひとつ以上のことをしています。映画だけを作っている訳ではありませんので」。2017年の第74回ヴェネチア国際映画祭審査員グランプリを受賞。
(2018年10月18日新宿武蔵野館にて鑑賞)


●ケン・ローチ監督『わたしは、ダニエル・ブレイク』(イギリス/フランス/ベルギー、2016年)。
2016年のカンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞。ケン・ローチが受賞するのは、アイルランド独立闘争を題材にした『麦の穂を揺らす風』に続いて2度目となる。2016年という年が、イギリスが国民投票でEU離脱を決め、トランプが合衆国大統領に就任した年であるという文脈においてみると、映像としても物語としてもいかにも地味な本作が受賞したことの意味が納得できる。
心臓発作で倒れたブレイクは、医師から仕事は当面無理といわれ、その間の社会保障を受けるべく役所を回るが、窓口はどこもブレイクを一人の人間として対応しようとはしない。19世紀自由主義の際立った特徴とされる働くもの食うべからずの自助主義は、21世紀の今もおそろしく健在である。
形ばかりの職探しをしなければ社会保障が受けられない状況に追い込まれたブレイクは、自分もまたこの新自由主義福祉国家のシステムの片棒をかつぐ道化と化していることに気づく。ブレイクの経験と人柄を信用したガーデニング会社から雇いたいとの連絡が来てしまうのである。偽りの求職活動であることを話すが、連絡してきた先方は怒って電話を切ってしまう。小さいことだが人間の基本的な善意や信頼関係を壊してしまうことに加担してしまったことが、ブレイクには耐えられない。ついには職業紹介所の外壁に「俺はダニエル・ブレイクだ!」と大書して叫び、引き籠ってしまう。
シングルマザーのケイティも、生まれ育ったロンドンでは住居を見つけることができず、福祉サービスに紹介されてイングランド北部のニューカースルに移住してきている。メインテナンスがなされていない公営アパートをあてがわれたケイティが、カビの生えた風呂のタイルを懸命にこすっていると、タイルの一枚がはげ落ちで割れるシーンがある。そのことがケイティの心を砕き、それは同時に観客の心も破砕してしまうのだが、こういうシーンにケン・ローチの映像表現の真骨頂を感じさせられる。
もうひとつ、フードセンターで配給された食糧を受け取るケイティが、その場で調理された豆の缶詰を空けて手で食べてしまうシーンがある。一瞬「ええっ?」と思ったが、ケイティを演じたヘイリー・スクワイアーズはケイティの追い詰められた衝動をうまく演じていた。一見突拍子もない場面のように見えるが、これは、グラスゴーでの実話に基づいた場面であるということが電子版『ガーディアン』紙の読者コメントに書かれていて、フィクションの持つリアリズムというわけでもないことを知った。
ケン・ローチは、1960年代にBBCテレビで、若い家族が、夫の仕事での事故と怪我をきっかけにホームレスとなり一家離散に追いやられるドキュメンタリー・ドラマ『キャシー、帰っておいで』(1966年)で鮮烈に登場し、その後映画に転じた。本作は、珠玉の代表作『ケス』(1969年)、『レイニング・ストーンズ』(1993年)、『マイ。ネーム・イズ・ジョー』(1998年)、『スィート・シクㇲティーン』(2002年)など、人間らしさを奪う貧困と、逆説的にも貧困と補完関係にある英国社会保障制度をテーマにした系譜の作品である。貧困や社会福祉制度に対するケン・ローチの無理解を指摘する声もあり、それらには一定の理もある。だが、それらの批判がケン・ローチの映画の問いかけに答えるものとなっていないこともまた明らかではないだろうか。ケン・ローチの映像表現の長短をうまくとらえた批評はまだ未出ではないだろうか。
(2017年4月23日ヒューマントラストシネマ有楽町にて鑑賞)

●The Stuart Hall Project, directed by John Akomfrah (UK、2013).
イギリスのカルチュラル・スタディーズの開拓者であるスチュアート・ホールの自伝的映像ドキュメンタリ。ジャマイカ出身、ロズ奨学生としてオックスフォードに学び、ニュー・レフト運動のオルガナイザーとして活動してきたばかりでなく、バーミンガム大学文化研究所の所長として、また放送大学の社会学教授として、既存の教育制度の中に対抗的拠点を築く活動もしてきたスチュアート・ホール。彼の既成制度内外における活動の軌跡は、彼自身が二人のヒーローと呼ぶレイモンド・ウィリアムズとE・P・トムスン、そしてホールを自分の後任として呼んだバーミンガム大学文化研究所の創始者であったリチャード・ホガートらの、それぞれかなり異なりながらもグラムシ的なパラダイムを共有した知的伝統と教育実践を継承した軌跡でもある。
コロニアルからポスト・コロニアルの時代における彼のグローバルな移動の経験は、ウィリアムズやホガートの究極的にはドメスティックな階級移動や地理的移動とは大いに異なる意味を持つものであることをこのドキュメンタリはよく伝えている。彼の実姉は黒人男性との恋愛を両親に否定されて回復され得ぬ精神的傷を背負ったという。ホール自身はイギリスで白人女性と結婚し、人種問題で社会が大きく揺れた60年代後半から70年代のイギリスのバーミンガムでむき出しの人種差別と向き合うことを余儀なくされる。
しかし、印象に残ったのは、マイルズ・デイヴィスのトランペットとともに本作品の基調となっている人種問題ではなく、ジェンダーと戦後社会民主主義についてのホールの発言である。ヒーローたるウィリアムズもトムスンも、家庭生活を持つ夫としての男のロール・モデルにはなりえなかったという。「ニュー・レフトの話はしないで。私の結婚生活は奴隷と同じよ」とパートナーから問われても、ホールも彼のヒーローたちも答えを持ち合わせていなかったという。また、70年代末の戦後社会民主主義の瓦解こそが、ホールにとって最も大きな政治的衝撃であったことも語られている。80年代のホールの反サッチャリズム運動は、そうした文脈において考えられるべきであり、そうしてみれば、その闘いが戦後労働党の一定の再評価やニュー・レイバーへの道につながっている面があることは、なんら不思議ではない。さらには、ホールが尽力して生み出したニュー・レフトとしての制度的な遺産は今ではほとんどが解体されてしまったといえるかもしれないが、ホールの実践が制度面での闘いの重要さを再認識させてくれるものであることも忘れたくない点である。
(2016年10月31日DVD視聴)

●リテーシュ・バトラ監督『めぐり逢わせのお弁当』(インド・仏・独・米、2013年).
2014年夏、インドのムンバイ訪問後、タイ航空での帰国便の小さなスクリーンで鑑賞。インド映画というと、私にはボリウッド映画という印象が強く、歌って踊ってのめくるめくメロドラマの展開が思い浮かぶ程度の存在でしかなかったが、これはいわゆる「アート系」の映画の秀作である。帰国してみると日本でも上映中で、しかも東京では一月以上ロードショウ上映になるような人気ぶりであったことを思い出す。ただし、大きなスクリーンで再鑑賞したのはしばらくしてのちで、さいたま芸術劇場で上映会があったときのことになる。
やや早い定年を迎えようという妻を亡くして一人暮らしの公務員サージャンと、小学生の子どものいる既婚女性の主婦イラが、間違って(?)配達されるお弁当を媒介に、それぞれの生を静かに問い直していくストーリーになっている。誰もが日常でふと感じることのある消し去ることのできない、生を求めるもがきのような感情を巧みに表現した作品で、こういう比較は安易にすぎるのだろうが、小津映画のような味わいがあって、日本も含めて欧米でも人気となった理由もそのあたりにあるに違いない。
主人公サージャンの部下となった、孤児として育った青年の人生物語が、人生の半ばから後半へと差し掛かる主人公二人の人生と対比されるように挿入されていて、それが主人公の公務員の老成と衰えの両面を映す鏡ともなって、主人公の自問と断念を導くひとつの要素となっているが、それはまた、次世代へのおだやかで明るい期待の表れでもあるように思われて、そうした効果があって、私たちはいささか静かにかつ穏やかにこの映画を観終わることになるのだろう。イラも夫と別れてシングルマザーとして旅立つ。
歴史人類学を専門とするインド人(ただし、アフリカとアメリカ育ち)の大学院生にこの映画の話をすると、彼女はなんにも知らないのねと言わんばかりに、インドのアート系映画で観るべき映画のリストを送ってくれた。そのリストを手掛かりにと思いつつも、この映画の後、インド系アート映画の世界を広げる機会を持てないままでいる。
DVDには日本発売のものにも監督と主演の二人のコメンタリーも収録されているもよう。購入した米国版は、コメンタリーの入ったディスクとの2枚組で、あまりぱっとしないがブックレットがついている。
(2014年9月15日タイ国際航空機内で鑑賞)


●リティ・パニュ監督『消えた画 クメール・ルージュの真実』(カンボジア/フランス,2013).
日本のベトナム反戦運動史を地方都市の事例から調べているにも関わらず、恥ずかしながら、ベトナムをはじめインドシナ諸国の現代史についてちゃんと学んだことがない。それでもベトナムについてはそれなりに知見を深めたつもりだが、ベトナム戦争に決定的な関わりを持ったカンボジアやラオスということになると、ほとんど何も知らないも同然である。ポル・ポトによる大虐殺があったということ以外、実情などについては知らなかった。
この映画は、自らがクメール・ルージュの共産主義化政策の中で家族を失い、13歳でたった一人でカンボジアを逃れたリティ・パニュ監督の、ポル・ポト革命政権下のカンボジア人生の回想記である。映画に生ま身の人間は出てこない。土人形を並べた箱庭を使ってのそのときどきの光景の再現と、それに挟み込まれるように挿入されている当時を記録した白黒フィルムで映像は構成され、それらを監督の経験・想起・問いかけからなるナレーションが結びあわせていく。静かだが、重い事実を突き放すと同時に深く観客に伝えるのに成功している巧みな映画である。
それは、感情の起伏を表現することのない素朴な土人形たちの表情とたたずまいのせいだろうか。感情表現を奪われた土人形のまなざしが、数百万人の虐殺されていったカンボジア人の声を最もよく届けてくれているのである。死者たちはどんな言葉を発したらいいのか、発すべきどのような声があるのだろうか――と問わずにはいられないような惨劇が4年間もの間進行していたのである。
たまたま時間があったので、監督のことも映画のこともよく知らないままとにかく久しぶりに渋谷のユーロスペースまで出かけて行った。偶然だが、幸いなことに、上映後に久郷ポンナレットさんのアフター・トークを聞くことができた。久郷さん自身、両親と兄弟の4人を殺され、1980年16歳のときに、留学中で難を逃れた長姉を頼って難民として来日した経験の持ち主である。映像で語られていたリティ・パニュ監督の体験と同じような体験をしてきた女性である。
彼女の話が素晴らしかった。トークの終わりの方で、軍事独裁政権が支配するということがどういうことなのかを身をもって体験し、平和な日常生活の尊さを深く知る彼女が、安倍政権に任せておくだけでは平和は守れませんよ、と一言。久郷さんは、いまは自分の体験をこれからの「世界平和」のために語っていくことにしたという。「世界平和」という、自分の中では陳腐化していた言葉が、彼女の声を得て言葉本来の重さを取り戻して胸の内にストンと落ちた感じがした。自伝『虹色の空 <カンボジア虐殺>を越えて1975-2009』(春秋社、2009年)もすばらしい。
(2014年7月12日渋谷ユーロスペースにて鑑賞)

●エドガー・ライト監督『ワールズ・エンド』(UK, 2013).
観たあとで調べてみたら『ホット・ファズ』(UK, 2009)の監督だった。この監督の作品は、現代社会への鋭い風刺があり、また過去のさまざまな映画作品や文化遺産のプロットの借用、シーンの引用やパロディー満載で成り立っている。『ホット・ファズ』は田舎に左遷させられた有能警察官が、村の古き良き伝統秩序を壊しかねない異分子を村民たちが結託して殺していく事態を暴いて立ち向かう話である。モンティ・パイソン張りのシュールレアルな場面づくりが随所に施されていて大笑いさせてくれるが、多様性を許容しない権威主義的現代社会への風刺が作品の根底にあることは明らかである。そこが実は大きな共感を呼んでいるにちがいない。
本作『ワールズ・エンズ』でも、多様性と共生を称揚しつつ実は画一的な合理性のもとに計算された市民社会管理への批判が話のベースになっている。田舎の個性あふれた古き良き自家経営パブというパブが、いまやスタバ化されているのである。イギリスのパブのチェーン化が進んだのは実は1950年代後半以降のことだから、いまさらスタバ化を指摘しても、という感じはあるのだが、スタバ化とかつてのチェーン化は似て非なるところがある、というのも確かだ。スタバ化は用意周到で、各店舗個性を強調しながら巧みな超合理的な経営管理がなされているのである。かつてのビール製造会社によるチェーン化はもっと素朴だった。スタバ化というグローバル化段階なのだ、今は。ちなみにスタバは、イギリスで毎年巨額の売り上げをあげながら、会計上の操作でイギリスでの納税をつい最近まで逃れてきた多国籍企業の一つで、イギリスでは評判は良くない。
主人公はリハビリを強要されているアル中患者である。4人の高校時代の同級生はみな社会的に成功してそれなりの地位を守りたい立場にいる。だが、当然だが、故郷の田舎を再訪した5人の中で、故郷が宇宙人に支配されつつあることに気付くのは社会的肩書きからは自由な(しかしアンハッピーな)アル中なのである。話のつじつま合わせにはいろいろ無理があるように感じてしまうが、そんなことをいうのは野暮というものだろう。
ライト監督には、そろそろまったく違う差風の作品を作ってもらいたいなあとも思う。次回作にもおおいに期待したい。
鑑賞した池袋シネ・リーブルでは、売店でイギリスの優良ビール「ロンドン・プライド」を安く売っていたのがうれしかった(プレミアム・モルツと同じ520円)。逃れたい仕事の合間に、ポテチとロン・プラを手に土曜夜の空いた最終上映を満喫。
(2014年5月17日池袋シネ・リーブルにて鑑賞)

●World in Action, vol.1 (UK, 1967-1991).
イギリスの民間テレビ番組制作会社「グラナダ・テレビジョン」が制作し、民放ITVで放映されたドキュメンタリー・シリーズ 'World in Action' の秀作12本を収録したのがこの2枚組DVDで、Network から2005年に発売。以下のトピックに関心のある場合には必見。
1.ドラッグ所持の嫌疑で逮捕起訴され、無罪になったミック・ジャガーへのインタビュー(1967年)
2.チェ・ゲバラの死(1967年)
3.ロンドンでのベトナム反戦運動とデモ(1968年)
4.ヴェトナム戦争で疲弊し戦争への不満をあらわにする現地ベトナムの米国兵たち(1970年)
5.ウガンダをクーデターで乗っ取った軍人アミンの腐敗と独裁(1971年)
6.ブラック・パンサーのメンバーの監獄での不審死(1971年)
7.ベトナム戦争に翻弄されるコントゥムの山岳民族(1972年)
8.スティーヴ・ビコの生涯と死(1977年)
9.西ドイツ赤軍メンバーへのインタビュー(1978年)
10.イギリス・マンチェスターの運営が破たんしそうなストレンジウェイ監獄の取材(1979年)
11.イギリスの動物解放戦線や動物実験関係者への取材を通じて動物実験の問題を提起(1981年)
12.バーミンガムのパブを爆破した嫌疑で16年間投獄されていた冤罪事件の6人 Birmingham Six への取材。治安当局の杜撰な操作と容疑者への恐るべき暴力行使。(1991年)
イギリスには民放テレビ放送があるが、日本やアメリカの民放とはまったくことなる思想のもとで発足した。日本での民放放送局は、番組スポンサーからの収入を主として経営されている。しかし、イギリスでは、番組のスポンサーになることはできない。番組と番組の間のコマーシャルの時間をスポット買いすることしかできないのである。スポンサーの意向によって番組の内容が左右されない制度作りがなされている。このDVDに収録されているような質の高いドキュメンタリー番組が制作され、放映されてきたのは、ジャーナリズムの伝統もあるが、そのような放送理念が制度化されていることにもよる。チャンネル4などは、実験的で教育的な番組を放送することが使命とされているので、BBCよりも「過激な」特集番組が放送されたりする。公共放送とは、民放と区別された国営放送をさすのではない。電波自身が public であり、電波に乗るものはすべて public broadcasting なのである。日本の放送人や政治家に、そうした発想を持つ人がいまどれくらいいるだろう。
(2014年4月3日~6日DVDで視聴)

●Mike Hodges 監督 Get Cater (UK, 1971)
当時、それまでに作られたイギリスのどの犯罪映画よりも冷徹かつ残酷な映画だと言われたのが、この Get Carter(『カーターを掴まえろ』)である。邦題は『狙撃者』。日本では人気が出ず、公開後今日に至るまで、ビデオ化もDVD化もされていないという。イギリスでは一般の人気も、批評家の評価も高い映画で、全国紙『ガーディアン』が2010年に行なった批評家による投票では、世界中の犯罪映画のうちで7位に入っている。ちなみに、1位は『チャイナタウン』で、5位に『羅生門』。
ロンドンで暮らす殺し屋のカーターが、イングランド北部の生まれ故郷のニューカースルに帰り、地元のギャングや実業家を相手に、殺された兄弟の復讐を実行していく話だ。1971年制作の作品で、当時の地方工業都市の風景にどうしても目が行く。60年代の華やかさは、ニューカースル郊外の田園地帯に住むギャングの親玉のお屋敷で開かれているドラッグ・パーティー関連の場面ぐらいにしかみられない。ニューカースルの街と人びとの表情や態度から読み取れるのは、貧困と苛立ち、諦めと退屈、自嘲と自己満足、冷笑とむき出しの金銭的・性的欲望である。こうした悲観的な基調はふつう、1960年代ではなく、1970年代のイギリス社会の特徴として連想されることが多い。カーターの復讐心の狂気化に手を貸していく新しい文化、すなわち、暴力、ポルノグラフィー、ハード・ドラッグなどの問題が深刻化したとされるのも70年代である。だから、この映画はもう10年あとの1981年制作だと言われても、違和感がない。一部はすでに現実のものとなり始めてはいたが、なにぶんに時代を予見した映画である。
ロンドン下町のギャング・カルチャーを経験的に知っていたマイケル・ケインは、暴力団のカルチャーでは家族、とくに母親は、侵されざるべき尊厳なのだと、DVDのコメンタリーで話している。これはサッチャー首相が称揚していくことになるモラルでもある。それはひとつの賞賛されるべきモラルなのかもしれないが、それだけであるならばそれは独善的なモラルでしかない。他者と社会はその外部に位置する荒野にすぎないのだから。このモラルがどこに行きつくのかを映画はたんたんと描いていくが、それはサッチャー以後のイギリス社会の展開によって実証されてしまった、ともいえる。
この映画に撮られている60年代末の地方工業都市のさまざまな風景のショットは、60年代という時代のイコンとなっている――よそ者への疑い深い視線を向けるパブの労働者階級の客たち、スラム街の安宿、波止場、廃墟となったままの高層駐車場ビル、石炭屑廃棄によって真っ黒な波を打つ海、賭博店の盲目の客、8ミリの非合法ポルノ映画。60年代寛容社会以降のイギリス社会のイメージを形成するのに、この映画は少なからぬ役割を果たしてきているといえるだろう。

マイケル・ケインは1966年制作の『アルフィー』で初のアカデミー主演賞候補となったが、ケイン演じるカーターのキャラクターには、アルフィーのキャラクターがうまく引き継がれている。主人公カーターの、憎み切れない魅力はそこにあるのだろう。程度は天地ほどの差があるが、アルフィーもカーターも、自己の欲望の代償を最後は払うという点も似ている。アルフィーを知る者は、意識しようとしまいと、どうしても『アルフィー』の野蛮な変奏曲として Get Carter を観ることになるだろう。もうひとつ強く思ったのは、この映画は、2006年制作の London to Brighton(日本未公開)のような、近年のすぐれたギャング映画の原点となっているということだ。
イギリスの犯罪映画史上の傑作という点でも、役者マイケル・ケインの素晴らしい演技という点でも、1960年代イギリス地方都市の類まれな映像記録という意味でも、Get Carter の日本語版DVDは発売されてしかるべきである。ちなみに『アルフィー』は、廉価版の日本語版DVDが出ている。
(2013年7月、DVDで鑑賞)

●キム・ギドク監督『嘆きのピエタ』(2012年、韓国)104分
キリストの死体をひざに抱いて嘆く聖母マリア像のことを「ピエタ (pieta)」という。映画の宣伝チラシの図像がピエタである。宗教的に正しい道徳的な強い信仰や行為を英語でpietyといい、日本語では敬虔とか孝行などの信心や行為を意味するとされている。
この映画を観に行ったのは、ヴェネチア映画祭で金獅子賞を受賞した作品という消極的な理由だった。あらかじめ内容を伝え知っていたわけでも、キム・ギドクという監督だからというわけでもなかった。しかし、この映画は、ストーリーと映像の両面で、強い衝迫力を持った確固たる社会派映画で、啓示的とさえ言いたくなるような驚くべき作品だった。
ソウルの鉄工所の街が舞台だ。鉄工所と言っても、どの工場も機械は1台か2台、一人あるいは夫婦だけで操業している超零細弱小経営。べらぼうな高金利をふっかけてくる闇金融からの借金で急場をしのごうとするが、すぐに首が回らなくなる。容赦ない借金取り立て人のガンドは、身体障碍者になれば借金が帳消しになるだけの保険金がおりるといって、あるときは5本の指を機械で切断し、あるときはビルから突き落として足を骨折させる。障害者となったものたちは、家族とともに最底辺の展望のない生活を強いられる。将来に悲観してついには自死を選ぶものもいる。そんなふうにして愛する家族を失ったミソンが、復讐を果たそうとする。
この映画の主題となっているのは、「嘆き」でも「慈悲」でもない。それは、強い怒り、憤怒、怨である。キム監督は日本語版パンフレットの中で、「愛を与えた後、その愛を一瞬にして奪ってしまう……というのが最初の構想」だったと話している。キム監督のピエタ解釈は、ミソンがマリアでガンドがその子イエスであるとするなら、むしろ冒涜的でさえあるといえるのだが、そう感じさせないのは、この作品が社会的な不正義を真正面から問うて揺るぎがないからである。キム監督は、グローバル資本主義の犠牲となって人びとが傷つけられているという現実があり、そこが審査員にアピールしたから金獅子賞を受賞することができたのだろうとインタビューで答えている。「今や国家もひとつの消費者金融のような存在になり得ます」とも。
この時代を鋭く深く記録した、語り継がれる寓話として、史上に長く残っていく作品である。
(2013年6月29日、新宿武蔵野館にて鑑賞)

●金子サトシ監督『食卓の肖像』(2011年、日本)103分
学園闘争がふきあれていた1968年10月、西日本一帯で、食用油「カネミライスオイル」による食品公害事件が表面化していた。福岡や北九州、五島列島、長崎で深刻な健康被害がみられた。顔をはじめとして全身に吹き出物がでる。毎朝目を開けられないほどの目やにが出る。脱毛する、下痢をするなど、多様な症状に被害者は苦しめられた。しだいに分かってきたことは、混入していたPCBやダイオキシン類が身体全体の機能に計り知れない被害を引き起こしているということである。子どもや孫の世代にもその被害は広がっていることも明らかになっている。カネミ油症事件から45年、しかし、いまなお健康被害の終焉には程遠い。
ほかの公害による健康被害同様、毒物と症状との因果関係を明らかにできる科学的知見はごくごく限られている。それなのに、企業や政府は、因果関係が科学的に明らかとなったものだけを狭く、狭く限定してしか被害を認めて来ていないし、認めようともしない。被害者の粘り強い訴えと運動が、またそれに応えようとする心ある支援者や医療者・研究者の長年の営為が、企業と国をようやく動かしてきたという構図が、カネミ油症事件にもあてはまる。 この映画が最もよく伝えていているのは、被害者認定の運動に携わってきた被害者とその家族のおだやかで、自然の育みとともにある豊かな生活である。毎日食べて生きていくということ、その食べ物をもたらす自然を壊さないということの意味を、静かに私たちに問いかけてくるのがこの映画だ。なぜ農薬を使わないようにしようとするのか、なぜ遺伝子組み換え食品ではダメなのか―ーこの映画に登場する多様な家族のみなさんの暮らしと言葉は、私たちにもう一度、心鎮めてそうした問題に向き合ってみるよう促す。
(2013年4月30日、新宿K's cinemaにて鑑賞)


●佐々木芽生監督『ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの』(2013年、アメリカ)87分
図書館司書のドロシーと郵便局員のハーブ。二人は米国美術界では有名なアート・コレクターである。妻ドロシーの給料は生活費に、夫ハーブの給料はアート購入費にして人生を送ってきた二人。住んでいるのはニューヨークの1DKのアパートである。そこに4,000点ものコンテンポラリー・アートの作品が所蔵されてきた。人生の終盤を迎えた二人のこの膨大な収蔵品の運命を追ったドキュメンタリーが本作である。
この映画は、いわゆるアーツ・マネジメントとして括られているアートと社会の関係研究の最も重要な課題に関して、いろんなことを考えさせてくれる――ミュージアムとは何か、一個人がアートを購入・所有するということはどういう文化的・社会的・経済的な意味を持つのか、パトロネージとは何か、若手や著名ではないアーティストに対して個人支援がはたす役割、公立美術館と民間美術館の違いは何か、コンテンポラリー・アートの収集・保存・継承はどうなされるべきなのか、ミュージアムのアーカイヴ機能の重要性、地方美術館が直面しているさまざまな困難と制約、コンテンポラリー・アートの教育普及活動の特別な意義……。
アメリカの50州に50作品づつを贈る。それぞれの美術館で展覧会が開かれ、そこにハーブとドロシーも招待される。各美術館ではさまざまな美術ワークショップが開かれる。それらの作品はインターネット上でも公開され始め、ヴァーチャルなハーブとドロシーの美術館が少しづつ形を作り始めている。
映画を観ていて、イギリスで行なわれてきている"Own Your Art"というアーツ・カウンシルの文化事業を思い出した。アートを所有してみたいが資金がない人たち向けに、2,000ポンド(日本円で30万円相当)まで無利子で貸し付ける制度である。この制度は、作品購入者を経済的・知的・文化的に支援することが究極の目的ではなく、作品が購入されることで、作品の作り手である無名の若手、とくに地方在住の作家の創作と生活を支援しようとするものである。購入者は、アーツ・カウンシルが認定した数々の画廊を通して購入しなければならないので、一定の質の補償と地方の中小の画廊の支援にもなっている。ちゃんと調べてはいないが、なかなかよくできた制度だという感想を持っている。数年前にイギリスのテレビで観た番組では、ほとんど焦げ付きがなく貸し付けたお金は回収できているため、貸付事業は毎年更新されて継続中と報じられていた。
監督は佐々木芽生。この作品には前作『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』があるが、こちらは未見。この映画の存在を教えてくれた福岡のKさんに多謝。
(2013年4月29日、東京都写真美術館ホールにて鑑賞)
●John Crowley監督 Is Anybody There? (UK, 2008)
75歳になるイギリスを代表する男優マイケル・ケインが、悪化していくアルツハイマー病を患う85歳の老人クラレンスを演じて秀逸。時代はサッチャー政権下の1987年、イングランド北部の小さな民営老人ホームにクラレンスは入所する。若い零細経営者夫婦には11歳の息子エドワードがいるが、彼の唯一の関心は死後の世界である。
クラレンスは奇術師の仕事をしていたが、一緒に仕事をしていた妻には立ち去られている。その後悔だけが日増しに募るような毎日のなかで、日常生活上の記憶はまだらになっていく。クラレンスはエドワードに奇術を教えることで、エドワードはクラレンスから奇術を教わることで、それぞれ、少しは安定した生の軌道を描き始めるのだが……。
大事な記憶も失って死んでいくクラレンスの描写は突き放されたもので、少しも感傷的なところがない。マイケル・ケインの現実世界での妻シャキラは、死にゆく老人を演じたケインのあまりに迫真の演技におののき、自分の妊娠中の娘にこの映画の鑑賞を禁じたという。(余計なことだが、シャキラの気持ちはよくわかる。自分自身、退院間もなくしてこのDVDを観たためか老いの過酷さがひどく身に染み、いささか長いウツ状態に入る引き金となった。)
暗い映画ではない。エドワードの両親は関係を修復し、エドワードも自分の生を生きていく。ハッピー・エンディングである。クラレンスの死は、人間だれしも歳をとれば死ぬというあたりまえの事実を示したものにすぎない。むろん、この当たり前の事実・摂理をそのまま受け入れられないのが私たちなのであることはそのとおりだ。そこにこの映画の価値はあると思うのだが、日本で公開されていないのはなぜだろう?
マイケル・ケインは、自己批評ある男の役柄を演じることを、プロの俳優としてのひとつの課題としてきているように思う。1966年の傑作「アルフィー」での、豊かな戦後社会における労働者階級出身成り上がりプレイボーイ役。1988年の「リトル・ボイス」での、一攫千金を夢見るしがない地方芸能マネージャー役。両作品とも、イングランド北部の労働者階級を巧みに描くことで知られた作家、脚本家が原作を書いている。「アルフィー」はビル・ノートンが原作、「リトル・ボイス」はジム・カートライトが原作である。こうした作品と役柄に果敢に挑戦して成功を収めているのがマイケル・ケインなのである。92分、John Crowley監督、日本未公開。
(2012年11月末、DVD鑑賞)
 クラレンス(Michael Caine)とエドワード(Bill Milner)
クラレンス(Michael Caine)とエドワード(Bill Milner)