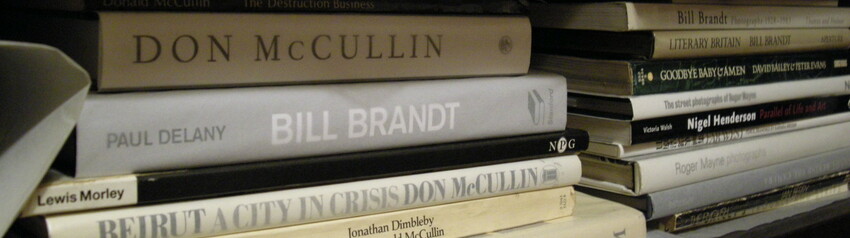●ケン・ローチ監督『わたしは、ダニエル・ブレイク』(イギリス/フランス/ベルギー、2016年)。
2016年のカンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞。ケン・ローチが受賞するのは、アイルランド独立闘争を題材にした『麦の穂を揺らす風』に続いて2度目となる。2016年という年が、イギリスが国民投票でEU離脱を決め、トランプが合衆国大統領に就任した年であるという文脈においてみると、映像としても物語としてもいかにも地味な本作が受賞したことの意味が納得できる。
心臓発作で倒れたブレイクは、医師から仕事は当面無理といわれ、その間の社会保障を受けるべく役所を回るが、窓口はどこもブレイクを一人の人間として対応しようとはしない。19世紀自由主義の際立った特徴とされる働くもの食うべからずの自助主義は、21世紀の今もおそろしく健在である。
形ばかりの職探しをしなければ社会保障が受けられない状況に追い込まれたブレイクは、自分もまたこの新自由主義福祉国家のシステムの片棒をかつぐ道化と化していることに気づく。ブレイクの経験と人柄を信用したガーデニング会社から雇いたいとの連絡が来てしまうのである。偽りの求職活動であることを話すが、連絡してきた先方は怒って電話を切ってしまう。小さいことだが人間の基本的な善意や信頼関係を壊してしまうことに加担してしまったことが、ブレイクには耐えられない。ついには職業紹介所の外壁に「俺はダニエル・ブレイクだ!」と大書して叫び、引き籠ってしまう。
シングルマザーのケイティも、生まれ育ったロンドンでは住居を見つけることができず、福祉サービスに紹介されてイングランド北部のニューカースルに移住してきている。メインテナンスがなされていない公営アパートをあてがわれたケイティが、カビの生えた風呂のタイルを懸命にこすっていると、タイルの一枚がはげ落ちで割れるシーンがある。そのことがケイティの心を砕き、それは同時に観客の心も破砕してしまうのだが、こういうシーンにケン・ローチの映像表現の真骨頂を感じさせられる。
もうひとつ、フードセンターで配給された食糧を受け取るケイティが、その場で調理された豆の缶詰を空けて手で食べてしまうシーンがある。一瞬「ええっ?」と思ったが、ケイティを演じたヘイリー・スクワイアーズはケイティの追い詰められた衝動をうまく演じていた。一見突拍子もない場面のように見えるが、これは、グラスゴーでの実話に基づいた場面であるということが電子版『ガーディアン』紙の読者コメントに書かれていて、フィクションの持つリアリズムというわけでもないことを知った。
ケン・ローチは、1960年代にBBCテレビで、若い家族が、夫の仕事での事故と怪我をきっかけにホームレスとなり一家離散に追いやられるドキュメンタリー・ドラマ『キャシー、帰っておいで』(1966年)で鮮烈に登場し、その後映画に転じた。本作は、珠玉の代表作『ケス』(1969年)、『レイニング・ストーンズ』(1993年)、『マイ。ネーム・イズ・ジョー』(1998年)、『スィート・シクㇲティーン』(2002年)など、人間らしさを奪う貧困と、逆説的にも貧困と補完関係にある英国社会保障制度をテーマにした系譜の作品である。貧困や社会福祉制度に対するケン・ローチの無理解を指摘する声もあり、それらには一定の理もある。だが、それらの批判がケン・ローチの映画の問いかけに答えるものとなっていないこともまた明らかではないだろうか。ケン・ローチの映像表現の長短をうまくとらえた批評はまだ未出ではないだろうか。
(2017年4月23日ヒューマントラストシネマ有楽町にて鑑賞)