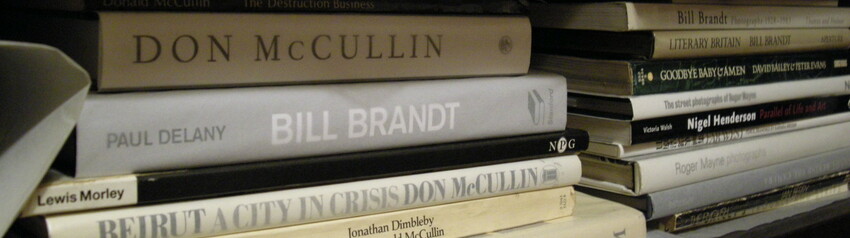●エドガー・ライト監督『ワールズ・エンド』(UK, 2013).
観たあとで調べてみたら『ホット・ファズ』(UK, 2009)の監督だった。この監督の作品は、現代社会への鋭い風刺があり、また過去のさまざまな映画作品や文化遺産のプロットの借用、シーンの引用やパロディー満載で成り立っている。『ホット・ファズ』は田舎に左遷させられた有能警察官が、村の古き良き伝統秩序を壊しかねない異分子を村民たちが結託して殺していく事態を暴いて立ち向かう話である。モンティ・パイソン張りのシュールレアルな場面づくりが随所に施されていて大笑いさせてくれるが、多様性を許容しない権威主義的現代社会への風刺が作品の根底にあることは明らかである。そこが実は大きな共感を呼んでいるにちがいない。
本作『ワールズ・エンズ』でも、多様性と共生を称揚しつつ実は画一的な合理性のもとに計算された市民社会管理への批判が話のベースになっている。田舎の個性あふれた古き良き自家経営パブというパブが、いまやスタバ化されているのである。イギリスのパブのチェーン化が進んだのは実は1950年代後半以降のことだから、いまさらスタバ化を指摘しても、という感じはあるのだが、スタバ化とかつてのチェーン化は似て非なるところがある、というのも確かだ。スタバ化は用意周到で、各店舗個性を強調しながら巧みな超合理的な経営管理がなされているのである。かつてのビール製造会社によるチェーン化はもっと素朴だった。スタバ化というグローバル化段階なのだ、今は。ちなみにスタバは、イギリスで毎年巨額の売り上げをあげながら、会計上の操作でイギリスでの納税をつい最近まで逃れてきた多国籍企業の一つで、イギリスでは評判は良くない。
主人公はリハビリを強要されているアル中患者である。4人の高校時代の同級生はみな社会的に成功してそれなりの地位を守りたい立場にいる。だが、当然だが、故郷の田舎を再訪した5人の中で、故郷が宇宙人に支配されつつあることに気付くのは社会的肩書きからは自由な(しかしアンハッピーな)アル中なのである。話のつじつま合わせにはいろいろ無理があるように感じてしまうが、そんなことをいうのは野暮というものだろう。
ライト監督には、そろそろまったく違う差風の作品を作ってもらいたいなあとも思う。次回作にもおおいに期待したい。
鑑賞した池袋シネ・リーブルでは、売店でイギリスの優良ビール「ロンドン・プライド」を安く売っていたのがうれしかった(プレミアム・モルツと同じ520円)。逃れたい仕事の合間に、ポテチとロン・プラを手に土曜夜の空いた最終上映を満喫。
(2014年5月17日池袋シネ・リーブルにて鑑賞)